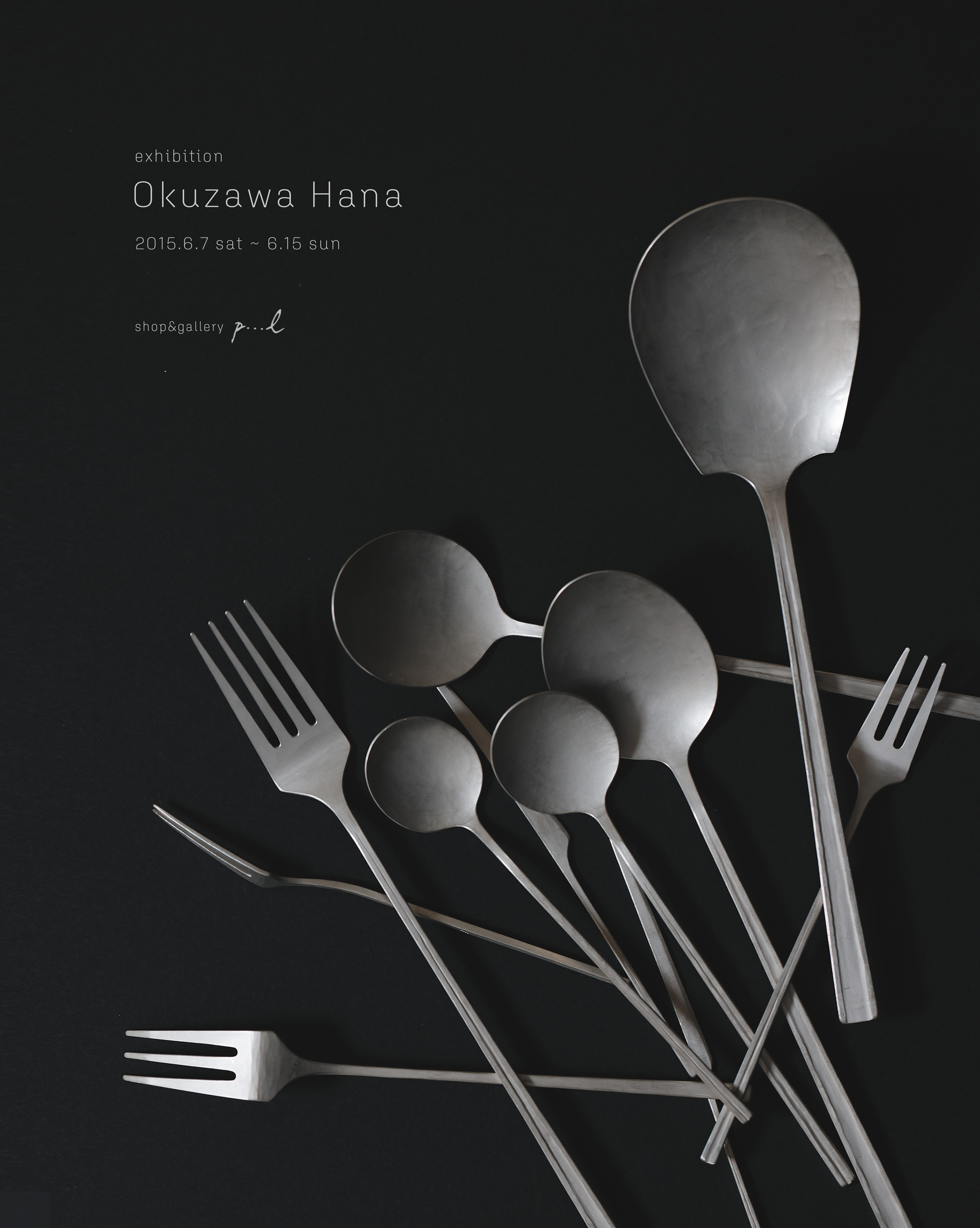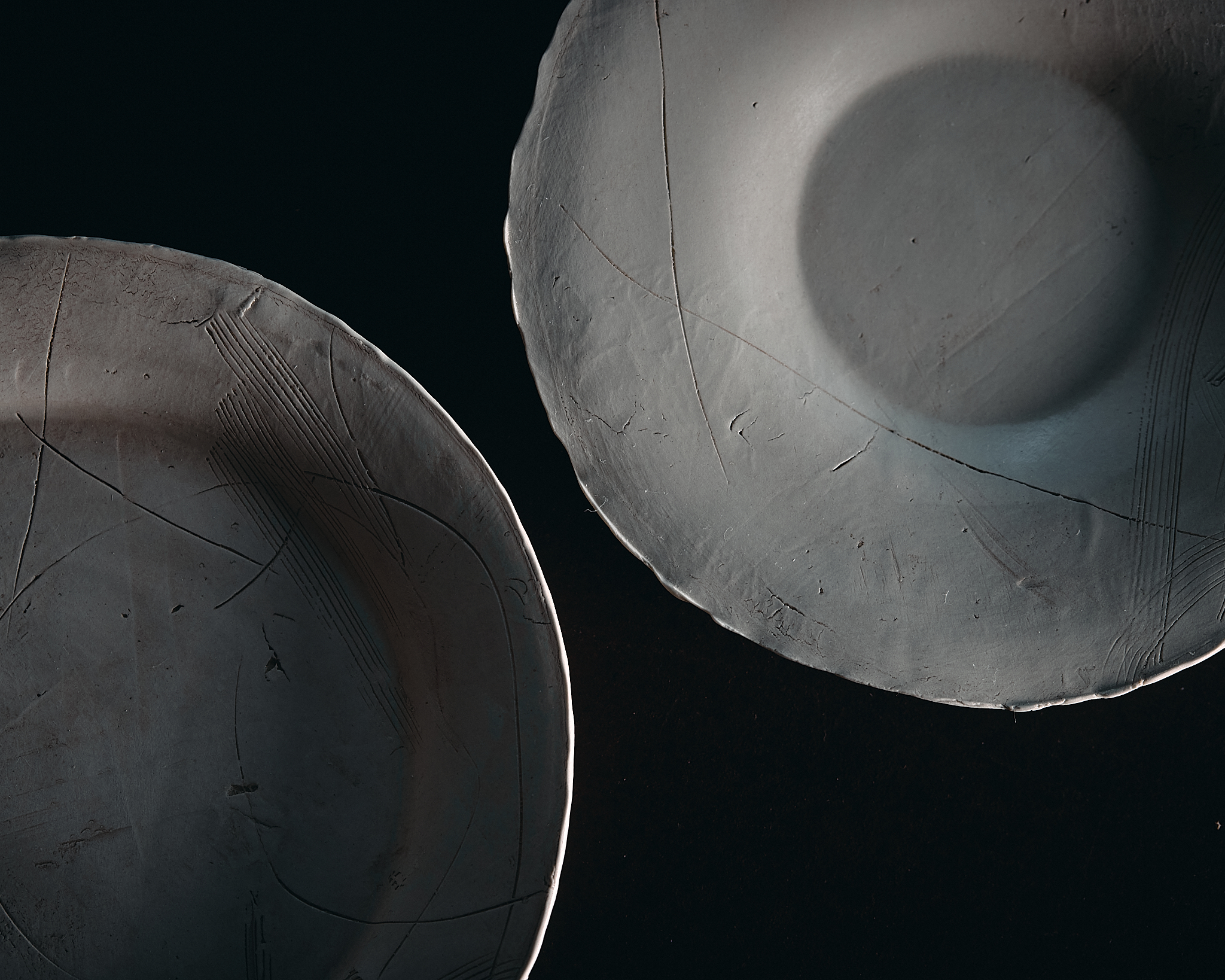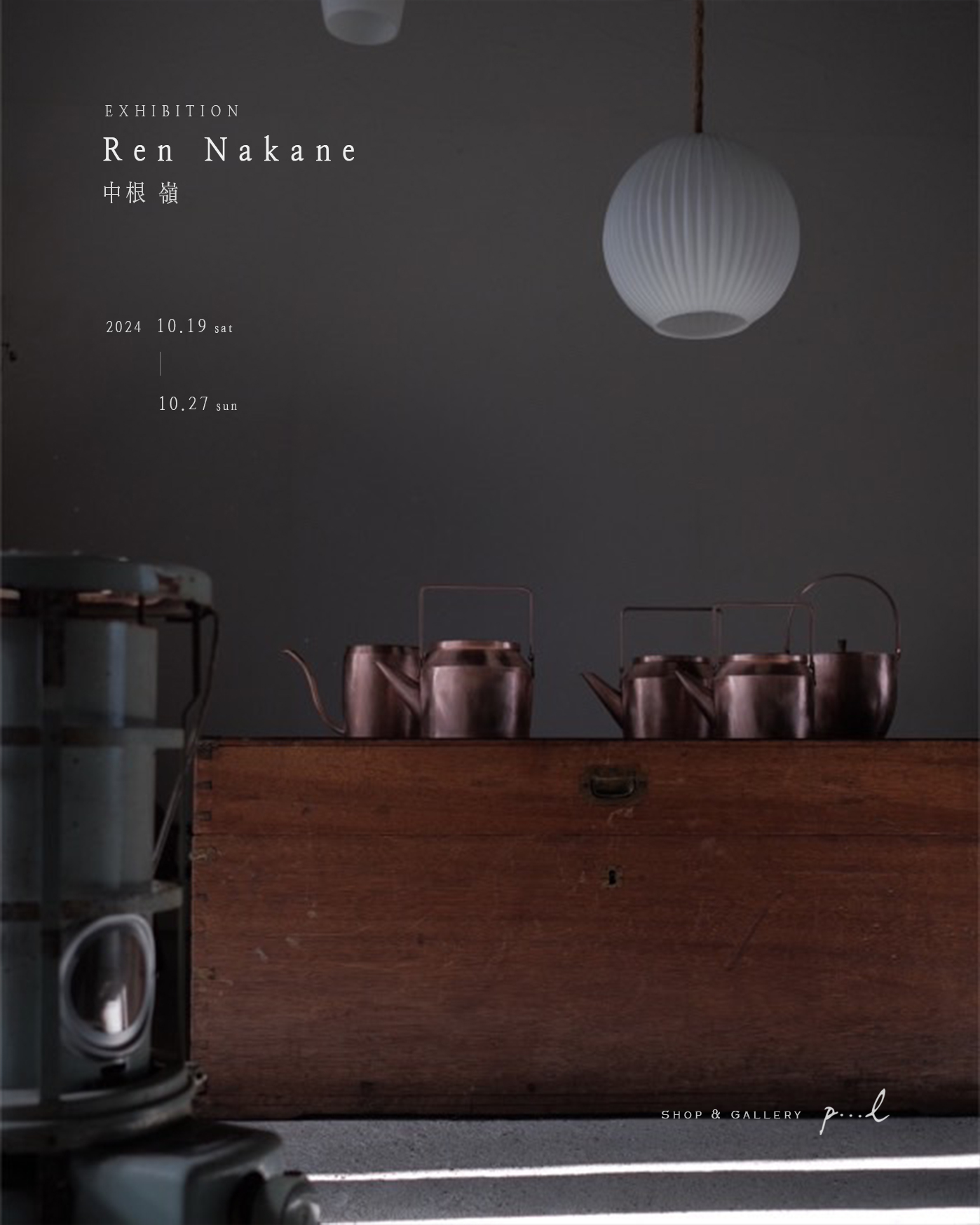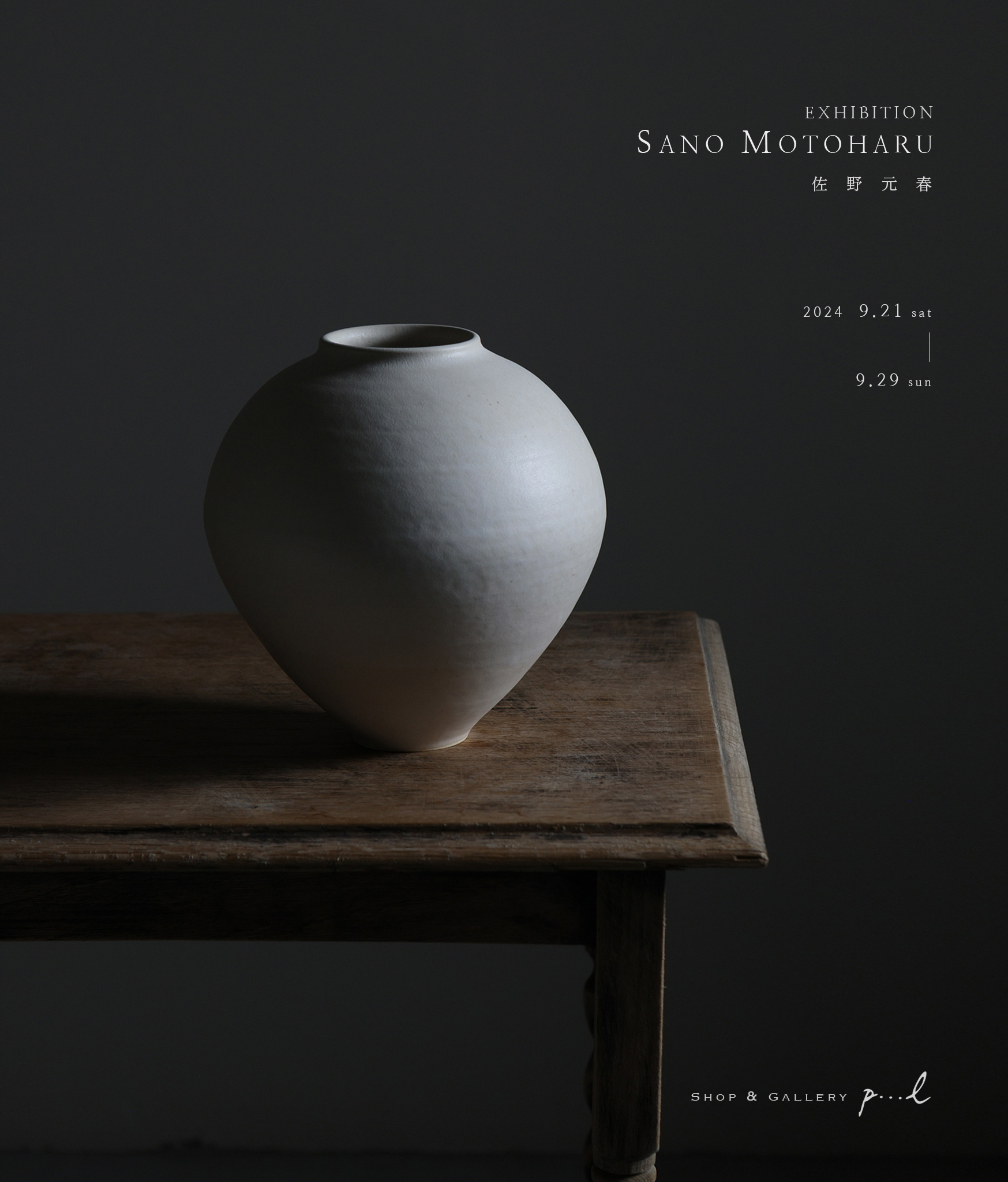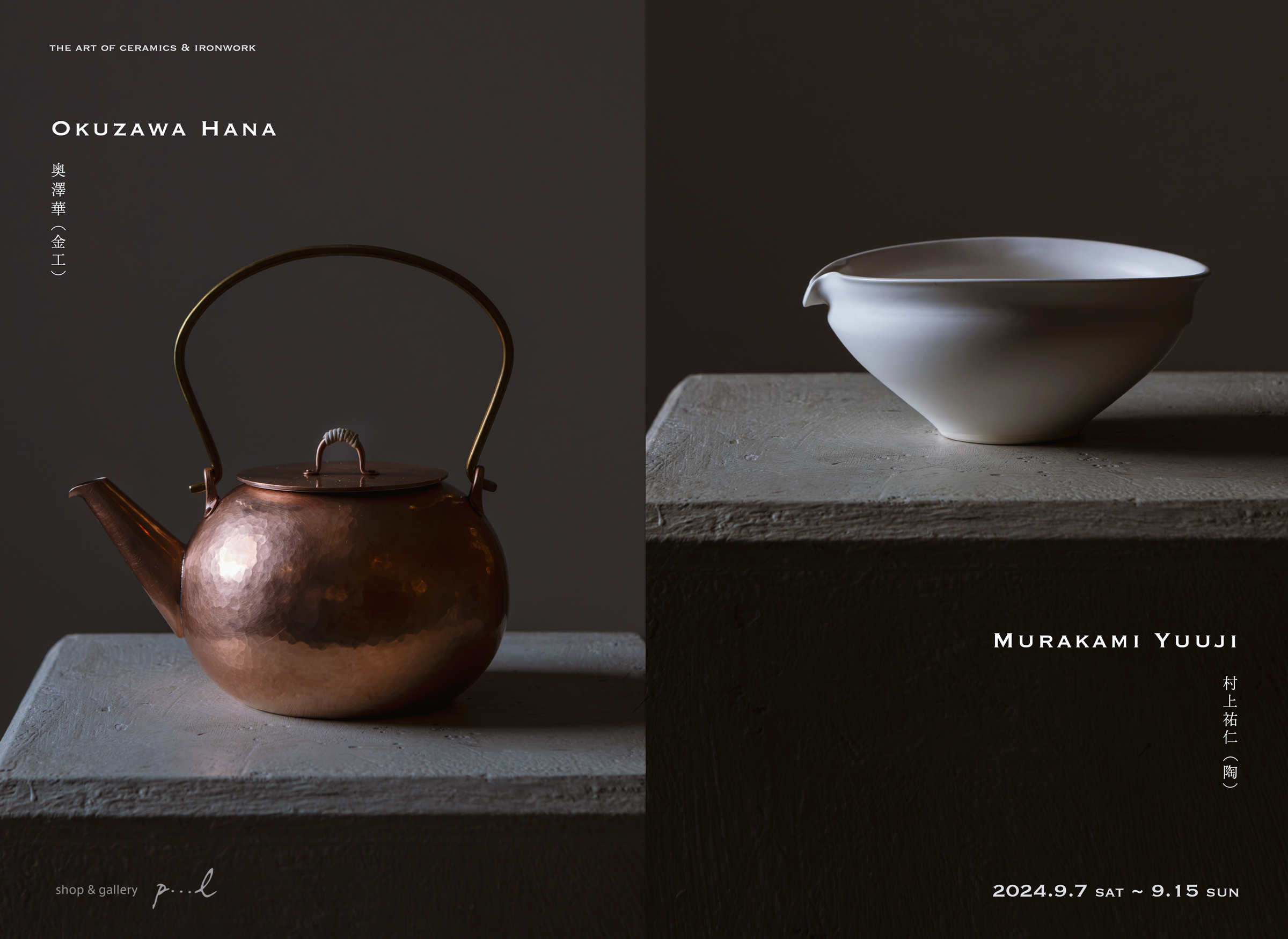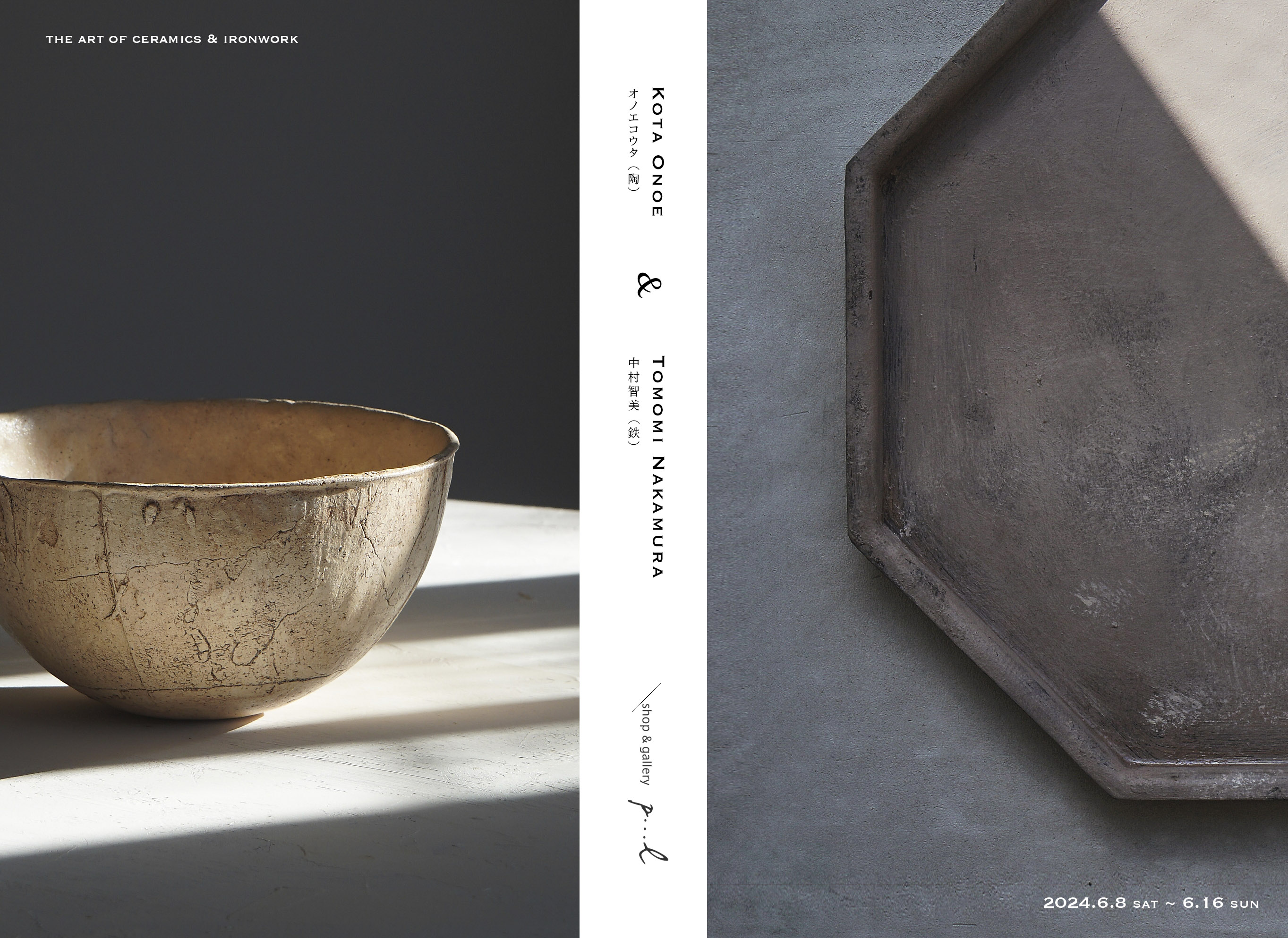永木卓 (RITO GLASS) 硝子展
~ 2025年 7月 04日
「器はそれ一つでどうにかなるのだろうか。
そこに入れるものがあって、使ってくれる人がいて、
使われて生きる道具を私は作りたいのだと思う。」
ritoglass(永木卓)さんはこう言います。
そんな彼のモノ作りは ” 引き算 “ の思想によって行われます。
作り手の色(個性)を押し出すよりも、使い手が自由に楽しめる余白のあるモノ作り。
モノクロームの写真のように、見る人(使う人)の想像力を掻き立てる。
そんな余計な色のない世界。
それが永木さんが求める” 引き算 “ によるモノ作りです。
彼は言います。
「足し算は使う人にして欲しい」と。
民藝運動の父である柳宗悦は、自身の著書の中でこんなことを言っています。
“ 嘗て美は凡ての共有であつて、個人の所有ではなかつた。
私達は民族の名に於て、時代の名に於て、その労作を記念せねばならぬ“
(柳宗悦「雑器の美」より)
名もなき職人たちが作った日用品に、美と手仕事の価値を見出した民藝。
そこに宿った美しさは、その時代、その土地に生きる人々が積み上げ、そして作り上げたものであり、個人の創造性(個性)を遥かに超えたものでした。
永木さんの器が持つニュートラルな美しさの中に、民藝に宿る美を見たような気がしています。
 永木卓さんの器で楽しむ Tea corner (料理家 西本かがり)
永木卓さんの器で楽しむ Tea corner (料理家 西本かがり)
料理家 西本かがりさんが手掛ける冷たい甘味とお飲み物を、永木卓さんの器で楽しむTea cornerを開催します。
作り手(作家)と使い手(料理家)が共に集うこの場所で、ガラスから伝わるもの、そこから感じられるものを体験、体感していただけれる場になればと思っています。ご予約は不要で、お席が空いていればどなたでもご参加いただけます。
詳細はこちらから
開催概要
| 期間 | 2025年7月19日(土) ~ 7月27日(日) ※月火水曜日はお休み |
|---|---|
| 時間 | 12:00 ~ 18:00 |
| 作家 | 永木卓 (RITO GLASS) Eiki Taku, 在廊日:19日(土) |
| 場所 | poooL 新店 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-8-11 #101 tel. 0422-20-5180 JR・京王井の頭線吉祥寺駅北口から中道通りを徒歩5~10分 |